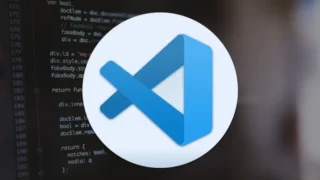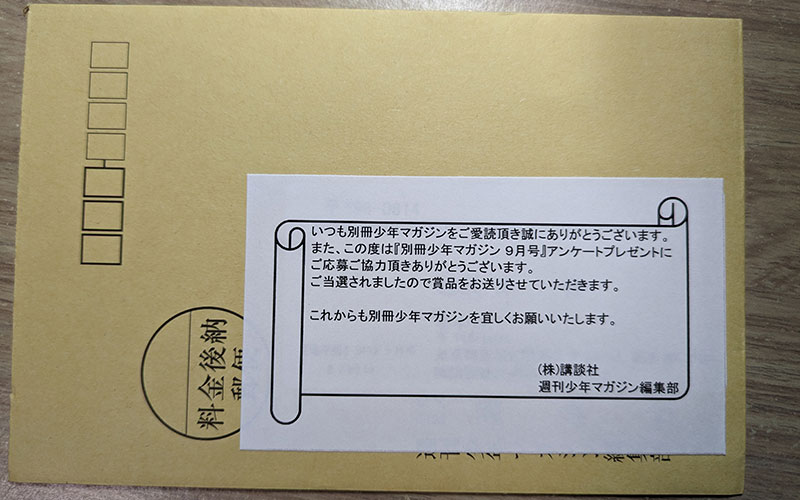以前より気になっていた、アガサ・クリスティー賞受賞作、逢坂冬馬(あいさか・とうま)著「同志少女よ敵を撃て」を読んだのでその感想です。
あらすじ
独ソ戦が激化する1942年、モスクワ近郊の農村に暮らす少女セラフィマの日常は、突如として奪われた。急襲したドイツ軍によって、母親のエカチェリーナほか村人たちが惨殺されたのだ。自らも射殺される寸前、セラフィマは赤軍の女性兵士イリーナに救われる。
「戦いたいか、死にたいか」――そう問われた彼女は、イリーナが教官を務める訓練学校で一流の狙撃兵になることを決意する。母を撃ったドイツ人狙撃手と、母の遺体を焼き払ったイリーナに復讐するために。同じ境遇で家族を喪い、戦うことを選んだ女性狙撃兵たちとともに訓練を重ねたセラフィマは、やがて独ソ戦の決定的な転換点となるスターリングラードの前線へと向かう。おびただしい死の果てに、彼女が目にした“真の敵”とは?
久しぶりの読書、また比較的厚みがありましたが、次々と読めました。
あらずじにもある通り、セラフィマを中心に運ぶ物語で、エンターテインメント性はバッチリだったのではないでしょうか。
訓練を経た彼女が最初にスコープを覗いたときのスピード感、高揚感は読んでいて気持ちが良かったです。
やがて独立小隊として各地を転戦する彼女たちですが、全員死亡のバッドエンドも頭をよぎる凄惨さ。
全滅はしませんでしたがまさか最初の戦死者があの人だったとは。
ネタバレになりますが、エピローグは1978年。終戦後30余年を経た年。
まさかギリギリ、ワタシが生まれたあとの話になるとは(苦笑)
巻末にはアガサ・クリスティー賞受賞に対するコメント等が掲載されており、これがデビュー作となるとは作者である逢坂氏のポテンシャルはいか程のものか。
一言ですげえ。
「推薦のことば」としてロシア文学研究者である沼野恭子氏の言葉があるのですが、
第二次世界大戦時、最前線の極限状態に抛りこまれたソ 連の女性狙撃手セラフィマの怒り、逡巡、悲しみ、慟哭、愛が手に取るように描かれ、戦争のリアル を戦慄とともに感じさせる傑作である。
というのが一番短く、かつ端的に書かれている感想ではないでしょうか。
いやあ、久々に良いものを読ませていただきました。
逢坂氏の次回作にも期待です。